
EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2009.08.07
2009年7月23日にECHAから、「成形品中の物質の要求事項のガイダンス」改定のドラフトが公表されました1) 。
2009年6月26日付のコラムでご紹介しましたが、既存のガイダンスの改訂や新規のガイダンスは、基本的には外部の専門家を入れて、ECHAがドラフトを作成し、以下の3段階の協議にかけられます。
今回公表されたドラフトは、「1.PEG」の協議にかけられるものです。ただ、ドラフトは途中段階のもので、特に問題となっている、SVHC(高懸念物質)の濃度算出に関する部分はまだ検討中ということで、今回の協議の対象ではありません。後日、修正されて協議にかけられます。
全体的に見ますと、ドラフトは大変わかりやすいものに整理されています。特に、対象物が物質や混合物2)を含む(あるいは、表面にある)のか、あるいは、その対象物が成形品と判断するのかの判断フローが改定され、わかりやすいものなっています。今回のコラムでは、この内容を簡単に紹介します。
判断フローの図を以下に示します。
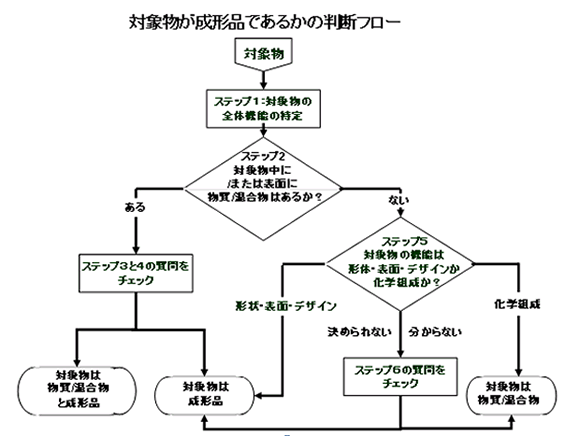
従来の判断ステップは、5段階で説明されていましたが、今回は図に示しますように6段階に整理されています。
ステップ1では、対象物の全体機能を判断します (先のガイダンスと同じ) 。
ステップ2では、対象物が以下の判断基準に適合するかを決定します。
このどちらかに適合すればステップ3に進み、どちらでもなければステップ5に進みます。
ステップ3では、従来のガイダンスのステップ4と同じで、以下の3種類の設問のチェックをします。
これらの設問の答えの大部分が「はい」であれば、その対象物は、容器またはキャリアーである成形品と物質/混合物であるとみなされます。この場合、物質/混合物は6条による登録対象になり、成形品である容器またはキャリアーは、7条の届出および33条の情報提供の対象になります。
これらの設問の答えの大部分が「いいえ」であれば、ステップ4進みます。
ステップ4は、従来のステップ5の設問になります。
これらの設問の答えの大部分が「はい」であれば、その対象物は、成形品であり物質/混合物は対象物と一体とみなされます。
他方、ステップ5では、対象物の機能が形状・表面・デザインに依存するならば成形品であり、対象物の機能が化学組成に依存するならば物質/混合物となります。
ステップ5でも判断がつかない場合は、ステップ6の設問で判断します。
これらの設問は、すべてに適用することはなく、ケースバイケースで異なることがあると思われますが、おおむね該当すれば成形品となります。
1) http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/guidance_sia.PDF(林 譲)