
EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2012.06.01
過日、利根川水系から取水する首都圏の浄水場の水道水から有害物質ホルムアルデヒドが検出され、多くの地域で断水するという事件が発生しました。厚生労働省と環境省からは、原因物質はヘキサメチレンテトラミンで、ヘキサメチレンテトラミンを含む産業廃棄物の処理が十分になされずに放流され、浄水場の水処理段階で分解し、ホルムアルデヒドが生成したものと考えられる発表されています。
報道等からは、廃棄物を委託された処理業者には、ヘキサメチレンテトラミンを含有する情報が伝えられていなかったとのことです。そのために処理が正しく行われず、ヘキサメチレンテトラミンを含有する廃棄物が排出されたことが原因です。
また、現行法令下ではヘキサメチレンテトラミンの排出基準が設けられていないとのことで、法令違反を起こしたのかの判断は出ていないようです。
もし、SDS(安全データシート)によりヘキサンメチレンテトラミンに関する必要な情報が正しく伝達され、その廃棄物をその情報に基づいて正しく処理された場合には、今回の事件が起こらなかったかどうかを考えてみたいと思います。
中央労災防止協会で公開されているSDSのうち、今回の事件に関連する項目の記載内容を抜粋しますと以下の通りです。
| 2.危険有害性の要約(GHS分類) | ||
| 物理化学的危険性 | 可燃性固体: | 区分2 |
| 健康に対する有害性 | 皮膚腐食性・刺激性 | 区分3 |
| 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2B | |
| 呼吸器感作性 | 区分1 | |
| 皮膚感作性 | 区分1 | |
| 生殖毒性 | 区分2 | |
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(腎臓 呼吸器) | |
| 10.安定性及び反応性 | ||
| 安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | 危険有害反応可能性 | 粉末や顆粒状で空気と混合すると、粉じん爆発の可能性がある |
| アルミニウム、亜鉛を侵す | 避けるべき条件 | 裸火禁止 | 粉じんの堆積を避ける |
| 混触危険物質 | 強酸 強酸化剤 (過酸化ナトリウム) | |
| 危険有害な分解生成物 | 加熱または燃焼すると分解し、有毒で腐食性のガス(ホルムアルデヒド、アンモニア、シアン化水素、窒素酸化物など)を生じる | 強力な酸化剤や強酸と反応し、有毒で腐食性のガスを生じる |
| 13.廃棄上の注意 | ||
| 残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする | |
| 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと | ||
| 汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う | |
| 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること | ||
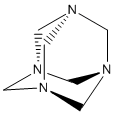
分子構造は、右図の通りです。テトラパックの各頂点に、N原子があり、窒素を結ぶ稜線の部分に-CH2-の結合があります。分子式は、C6H12N4です。
2項の「危険有害性の要約」に示しますように、有機物ですので可燃性であり、有機アミン化合物であることから健康有害性としては、皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性、呼吸器感作性、皮膚感作性、生殖毒性があるとされています。
このような健康有害性だけですと、化学物質を扱う事業所では通常使用される保護具を着用し、もし手に付着すれば素早く洗う等の応急措置をとれば大きな問題はないと思われます。また、間違えて飲み込んだ場合の有害性の分類はなく、後述します加水分解性を利用して、医療の現場では膀胱炎、尿路感染症、腎盂腎炎の治療に用いられていることもあるようです。
今回の事件からは、10番目の項目の「安定性及び反応性」の内容が重要です。
可燃性ですのでそれに対する注意が必要です。反応性については、加熱や燃焼した場合に今回問題となったホルムアルデヒド等の有毒ガスが発生します。また、強力な酸化剤、強酸に接触するとやはり有毒ガスが発生します。
これからだけでは今回の浄水場で起こった事件の予測は難しく思います。ただ、環境省から出されている「化学物質の環境リスク評価」に「酸の存在下で加水分解する」と記載されていることを考えると、十分な注意も必要です。
今回の事件では、浄水場の水処理工程でホルムアルデヒドが生成しています。前記の情報も含めて考えられることは、水処理工程で使用される次亜塩素酸ナトリウムが存在することによる(報道にもありましたが)加水分解の可能性があります。
正確な反応機構はわからないのですが、ホルムアルデヒドが生成したことを考えると、単純には以下のような分解反応が起こっていると考えることができます。
C6H12N4+6H2O→6HCHO+4NH3
SDSの13項「廃棄上の注意事項」には、具体的な処分方法についての記載はありません。今回のケースでは、廃棄物処理業者に処分法の選択が委ねられることになります。廃棄処理に当たっては、比較的マイルドな条件下でも加水分解の起こる可能性があることの注意喚起が必要かもしれません。
EUのREACH規則では、10t以上の物質についてはCSRの作成およびSDSへの暴露シナリオの添付が義務付けられています。しかし、CSRや暴露シナリオには、当該物質のCSR、暴露シナリオのみの要求が主体で、環境中に放出された後の分解物質の影響についての評価は求められていないようです。今後サプライチェーン全体を通しての化学物質管理をする上で、廃棄段階での分解物についての情報も重要な場合があり、SDSの13項においては、廃棄する際に必要となる情報も記載が必要な気がします。
(林 譲)