
電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2013.11.01
RoHS(II)指令は第4条による特定有害物質の含有制限を求め、適合性を第7条のCEマーキングで行うことを要求しています。CEマーキングによる適合性確認は整合規格に適合していることで行いますが、RoHS(II)指令の整合規格として「EN50581」が告示されています。
EN50581が求める適合性確証データの基本となるサプライチェーンマネジメントの要点をまとめてみます。
EN50581は、構成する技術文書の中の「材料、部品、及び/または半組立品に関する文書」として、必要とされる技術文書の種類を示しています。
この4種類の文書は「and/or」で採用するとしています。andにするかorにするかは、製造者の次の評価(アセスメント)に基づくとしています。
特定化学物質の含有/非含有が不明な物質に対して、技術的判断を加える必要があります。技術的判断は電気電子業界で利用されている技術的情報や電気電子製品に使用されている材料や部品のデータシートに基づいて行います。
調達する材料、部品や組立品などに特定化学物質を含有するリスクの一次審査を行い、次に含有の可能性を評価することになります。
技術的判断は技術者(評価者)の技術的知見に頼りますが、評価する技術者の要件はEN50581に記述はありません。ISO9001マネジメントシステムを構築していれば、設計・開発のレビュー(7.3.4)、設計・開発の検証(7.3.5)や設計・開発の妥当性確認(7.3.6)の参加要件などが評価する技術者の要件に利用できます。
評価の技術情報として「電気・電子製品-規制物質の濃度定量-サンプリング手順-指針(IEC/PAS 62596:2009)」などが参考になります。特定化学物質を含有する可能性が高い部材を使用している材料、部品や組立品に着目することになります。
製造過程の中で追加される部材(はんだ、塗装、接着剤等)も評価の対象として捉えられるべきとされています。これらは設計文書に記載されてなく、工場手配品になっている場合が多々あります。作業標準書(SOP)などの確認が求められます。
自社内のRoHS(II)指令対応はほぼ終わったが、材料や部品のサプライヤーやめっきなどの委託加工先の順法確認に苦慮している状況が多いようです。
EN50581では、「サプライヤーの過去の経験」や「サプライヤーの出荷試験や検査の結果」から評価するとしています。この評価はISO9001などの品質マネジメントシステムの1つとして手順を確立しておくことが必要です。
ISO9001では、サプライヤー評価を定期的に行う手順を定めていると思います。評価項目はQ(品質)C(コスト)D(納期)が中心で、ISO14001(環境マネジメントシステム)との統合システムではE(環境)関連の評価も含まれることがあります。
古い資料ですが、RoHS Enforcement Guidance Document May 2006では、RoHS指令コンプライアンス保証システム(CAS:Compliance Assurance System)の構築が求めています。構成要素として以下を求めています。
要点はCASを独自のシステムとして構築をするのではなく、既存の品質マネジメントシステムに統合して、日常的に管理することです。
日常的に行っているサプライヤー評価システムを利用することになりますが、RoHS指令の特定有害化学物質の非含有やREACH規則のSVHC含有情報の提供要求などを組み込む必要があります。
手順としては、取引開始にあたり、取引契約書、図面や要求仕様書に特定有害化学物質の非含有の要求(用途の除外は明記)を明確にします。
次に取引開始時及びその後の評価では、ISO9001で使っているサプライヤー評価手順に「調達する部品や材料の特定有害化学物質の含有の可能性」評価とサプライヤーのCASの評価を行います。
例えば、評価をa、b、c、dにランク付けなどをしますが、そのランクの基準は他のQCD評価項目に順じて決めます。
サプライヤーのCAS評価は、ISO9001の第二者監査に相当しますが、必ずしもISO9001の仕組みの監査ではなく、調達する部品や材料に関連する事項を中心にします。
BOM Checkでは、「材料、部品、半組立品に特定化学物質の含有の可能性」「サプライヤーの信頼性格付け」から、「サプライヤーによる自己宣言」「 契約上の合意」「材料宣言」「分析試験結果」の文書の組合せをマトリックスで示しています。
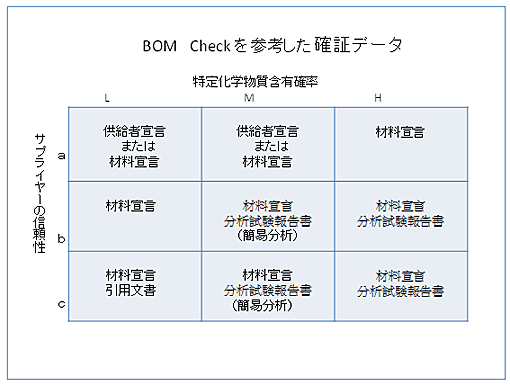
日本企業の多くは、サプライヤーの信頼性がc(悪い)、含有確率がH(High)の対応をしています。
サプライヤーや含有確率の評価が明確になっていない、評価に自信がないなど場合に、安全側にと信頼性c、含有確率Hにしているようです。
例示の確証データの組み合わせ図では、サプライヤーの評価がcからaに育成すると、含有確率Hであっても、分析試験報告書が不要となります。
外部分析機関に分析を依頼した場合の分析費用は、蛍光X線分析で5,000円/1検体、ICP分析で2万円/1検体程度です。コスト低減は製造業にとって重要な課題です。
サプライヤーの評価と調達する部品や材料に特定化学物質が含有する可能性で、収集する確証データが変えられることを理解することが重要です。
次回は続きとしてハザード管理とリスク管理について解説します。
(松浦 徹也)