
EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2016.11.04
労働安全衛生法の化学物質管理について、ラベル表示対象物質がSDS交付対象物質の所謂640物質に拡大、およびこれらの物質を新たに使用する場合等のリスクアセスメントの義務化が平成28年6月1日に施行され、5か月が経過しました。これまで企業の方からリスクアセスメントの進め方について多くのご相談を頂いていますが、その中で、「使用している物質が640物質にあるかが分からない」とのご相談が多くあります。これは同じ化学物質であっても異なる名前が付けられていることが原因です。今回のコラムでは、化学物質の名前の付け方についてご紹介します。
労働安全衛生法で指定される化学物質名は、国際的に決められているIUPAC命名法による化合物名を原則とし、日本語名の片仮名書きは日本化学会制定の字訳方式を採用することになっているとのことです。1)
平成28年6月に経済産業省・厚生労働省から出されましたリーフフレット「-GHS対応―化管法・安衛法におけるラベル表示・SDS提供制度」2)では、対象となる化学物質のCAS番号が記載されていますので、検索は大変楽になりました。
しかし、そこに記載されている物質名が入手したSDSの名称と異なっていることがあります。安衛法関係で規制の対象となっている化学物質名を例に挙げて、どのような名称があるかをご紹介したいと思います。
安衛法のラベル表示およびSDS交付対象物質となる「施行令別表9」にプロピルアルコールがあります。他方、有機溶剤中毒予防規則の対象となる「施行令別表第6の2有機溶剤」にはイソプロピルアルコール(CAS 67-63-0)があります。
ご質問の一つに、イソプロピルアルコールはプロピルアルコールと違うのかというものがあります。結論としては、プロピルアルコールは、ノルマルプロピルアルコールとイソプロピルアルコールの2物質の総称です。プロピルアルコールは、下記に示しますプロパンの水素(H)の一つが水酸基(ヒドロキシ基又はヒドロキシル基とも呼ばれる:-OH)と置き換わったものの総称です。

上記のようにプロパンの3個の炭素(C)に、左から1、2、3と番号を付けます。1番目の炭素の水素1個が水酸基(-OH)に置き換わったものが、ノルマルプロピルアルコールであり(なお、3番目の炭素は1番目の炭素の同じ性質です)、2番目の炭素の1個の水素が(-OH)に置き換わったものがイソプロピルアルコールです。
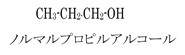
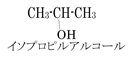
イソプロピルアルコールをNITEで提供されていますCHRIP3)で、CAS番号から検索しますと、日本語名は「プロパン‐2-オール」、別名として「イソプロパノール」、「イソプロピルアルコール」、「2-ヒドロキシプロパン」や「2-プロパノール」等が挙げられています。
このように、同じ化学物質であっても異なる名前が付けられる原因は、その化学物質をどのように見るかによって相違するといえます。例えば、画家が絵を描く際に、対象物を観察する視点が異なれば、描かれる絵も異なることに似ているのではないかと思います。
また、フタル酸ジノルマルブチル(DBP)、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)等のフタル酸エステル類が施行令別表9にリストされています。ご承知のように多くのフタル酸エステル類は、EU REACH規則の認可対象とする候補物質(candidate list substances of Very High Concern for Authorisation)に収載され、そのうちDBPやDEHPはEUで使用するには認可が必要な物質になっています(附属書XIVに収載され、現時点では認可申請の期限も終わっています)。
これらの物質の主たる構成基部分のフタル酸については、CHRIPで下記の名前が示されています。

CAS番号:88-99-3
日本語名:オルソフタール酸
別名:フタル酸
英語名:Orthophthalic acid
英語別名:1,2-Benzenedicarboxylic acid
フタル酸は、2個のカルボキシル基(-COOH)がベンゼン環の隣にある2個の炭素に結合しています。この化学物質は、フタル酸という名称の他に、1,2-Benzenedicarboxylic acidとも命名されます。ベンゼン環の隣同士の位置にある炭素を示す「1,2-」にカルボキシル基が結合していることを意味します。フタル酸という名前では、ベンゼン環にカルボシル基結合していることを知らなければ、「オルソフタール酸」の意味が理解できないかもしれません。
なお、安衛法の対象物質ではありませんが、ベンゼン環に2個のカルボキシル基が結合した化学物質としては下記の2物質があります。
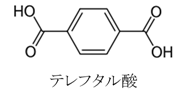
CAS番号:100-21-0
日本語名:テレフタル酸
別名:ベンゼン-1,4-ジカルボン酸
:p-カルボキシ安息香酸
:p-ジカルボキシベンゼン
:p-フタル酸
:p-ベンゼンジカルボン酸
英語別名:1,4-Benzenedicarboxylic acid
:Benzene-1,4-dicarboxylic acid
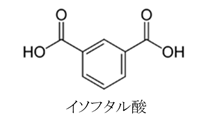
CAS番号:121-91-5
日本語名:イソフタル酸
英語別名:1,3-Benzenedicarboxylic acid
:m-Phthalic acid
昨年末に「オルト‐トルイジン」による膀胱がん発症の事案の公表がありました。このため、特化物に指定され、平成29年1月から施行される予定ですが4)、「オルト‐トルイジン」についても異なる名前があります。この物質もEU REACH規則のcandidate listに収載されています。
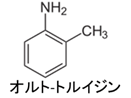
CAS番号:95-53-4
別名:1-アミノ-2-メチルベンゼン
:2-アミノトルエン
:2-メチルアニリン
:2-メチルベンゼナミン
:2-メチルベンゼンアミン
:o-トリルアミン
なお、「オルト‐トルイジン」に似た名前の化学物質として、残留塩素の測定に使用されていましたが、現在では使用が禁止されている「オルト‐トリジン」があります。図に示しますように「オルト‐トルイジン」が2分子結合したものです。その構造と別名は次の通りです。「オルト‐トリジン」は安衛法では製造の許可を受けるべき有害物として施行令別表第3(特定化学物質第1類物質)にリストされ、ラベル表示およびSDSの交付が必要です。

CAS番号:119-93-7
別名:3,3'-ジメチルベンジジン
:3,3'-ジメチル-[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジアミン
:4,4'-ビ-o-トルイジン
また、残念なことに「MOCA」による膀胱がんの発症事案も報道されました。この物質は安衛法では特定化学物質として規制されていますが、いくつかの別名があります。
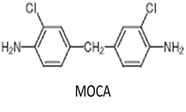
CAS番号:101-14-4
別名:3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン
:4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン
:ビス(4-アミノ-3-クロロフェニル)メタン
:4,4'-ビス(2-クロロアニリノ)メタン
:4,4'-メチレンビス(2-クロロアニリン)
英語別名:2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline
なお、MOCAもEU REACH規則でcandidate listに収載され、また、EUで使用するには認可の取得が必要は物質として附属書XIVに収載されています。認可申請期限は2017年11月22日です。
以上、羅列的に複数の名前が付けられる物質の例をご紹介しました。SDSで通知される物質名が、安衛法で指定されている名称と異なり、対象物質であるかの確認をするのにご苦労されることがあるかも知れませんが、CHRIP等を活用すればSDSで通知されている物質名で検索することが可能です。検索ができれば、適用される法律が確認できます。
ただ、安衛法では、指定されている640物質以外の物質についても、GHSで危険有害性があれば、使用される従業員の健康と安全のために、ラベル表示、SDSの交付やリスクアセスメントの実施が努力義務とされていますので、対応していただくことをお願いしたいと思います。
参考資料
1)http://cicsj.chemistry.or.jp/14_5/hata.html
2)http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/files/GHSpamphlet201606.pdf
3)http://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
4)http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11305000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Kagakubushitsutaisakuka/0000134678.pdf
(林 譲)