
電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2013.01.11
2013年はEUの改正RoHS指令〔以下、RoHS(II)〕のCEマーキング対応の義務が始まり、FAQも公示されたこともあって、日本企業にとっても新たな対応の始まりの年となります。RoHS(II)への関係者の関心も、「法規制の最新情報や解釈」から「自社の具体的な対応策」に移っているようです。
すでにEMC指令等のCEマーキングを貼付して製品を輸出している企業もRoHS(II)指令に関する「CEマーキングの技術文書の記述」に関心を高めています。
2012年12月21日付けコラム、2012年12月28日付けコラムでCEマーキングに関する規則や決定、整合規格を解説していますが、改めてRoHS(II)におけるCEマーキング対応について記述してみます。
CEマーキングには従来から日本企業も対応してきましたが、RoHS(II)指令によるCEマーキングは特定有害化学物質の非含有という新たな視点での対応であり、多くの戸惑いを与えているようです。
従来のLVD指令やEMC指令などの適合性確認は、最終製品で行うことができました。
一方、RoHS(II)指令の適合性確認は、EN50581の前文に「“均質材料”のレベルで適用される制限については、複雑な製品の製造業者にとっては、最終組立製品に含まれる全ての材料に独自の試験を実施することは非現実的である」とあるように、部材レベル、それも「均質材料」での適合性確認はサプライヤーに依存しなくてはならないという現実があります。
すなわち、CEマーキングは川下(輸出)企業の義務ですが、その対応を川中、川上企業に求める必要が生じています。これまで、川下企業は上流企業(サプライヤー)にグリーン調達基準の要求やJAMP AISによる情報提供などを求めてきました。サプライチェーンは階層が深く、また複雑に入り混じっており、まさにネットワークになっています。川中企業は多くの川下企業からさまざまな経路で、電気電子業界固有の「均質材料」レベルでの適合性確認が要求されて、エンドユーザーに複数の川下企業を顧客としている場合や電気電子業界以外の顧客が多いほど要求が違うことなどで困惑を深めています。
サプライチェーン管理については、EN50581やJIS Z 7201(製品含有化学物質管理-原則及び指針)などで対応が示され、各社はこの仕組みを自社に取り込むことになります。例えばEN50581は、調達部材の管理は「リスク管理」として次のように要求しています。
リスクアセスメントのために、サプライヤーから調達部材に関する文書を収集します。
この3種類の情報はすべて収集することは要求されていません。リスクにより集める情報は違ってきます。
情報の評価では、評価手順を規定することを要求し、注記としてIEC/TR 62476(電気電子機器における物質の使用制限に対する製品の評価のためのガイダンス)を示しています。IEC/TR 62476では、EN50581の各種情報をより具体化し、各要求事項とISO9001とISO14001の要求事項との対比を明確にしています1)。
BOM Check(エンバイロン社)では「ENVIRON Guide to Using BOMcheck and EN 50581 to Comply with RoHS2 Technical Documentation Requirements」で、情報の評価を「調達する部材に特定有害物質が含有する可能性」と「サプライヤーの信頼度」のマトリックスで決定するとしています2)。
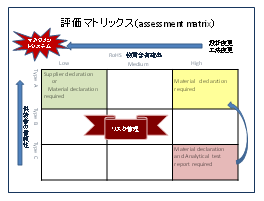
図はBOM Checkの図に筆者が追記したものですが、特定化学物質の含有確率の高い部材についてサプライヤー(供給者)の信頼性が低い場合と、特定化学物質の含有確率の低い部材についてサプライヤーの信頼性が高い場合では、要求する文書、情報が異なることを明示しています。
「調達する部材に特定有害物質が含有する可能性」と「サプライヤーの信頼度」の確定手順をどのように行うのかが、重要要素になります。
特定有害物質の含有の確率については、IEC/PAS 62596(電気・電子製品-規制物質の濃度定量-指針)の附属書Bに主要部材についてのHg、Cd、Pb、Cr(VI)、PBB、PBDEの存在確率が示されています3)。
サプライヤーの格付けの具体的な国際規格は存在していなく、ISO9001のようなマネジメントシステムにより、評価を行うことになります。川下企業は、ISO9001によるサプライヤー評価は従前から行い、RoHS指令などによる具体的な要求は川下企業の(グリーン)基準調達などで行い、評価しています。
日本企業は一般的にEN50581などが要求するリスク管理が不得意です。特定有害化学物質の存在確率とサプライヤー評価により要求する情報を変えることは理解できるのですが、実際の行動では摘発回避のために安全に安全を重ねて、全部材について「特定有害化学物質の存在確率が高く」「サプライヤー評価が低い」と評価して、「サプライヤーとの契約書」「材料証明書」「分析試験結果」の一式を要求しがちです。
IEC/PAS 62596に記載されていない部材、サプライヤー評価は、企業自ら第三者にわかるように実施しなくてはならないのですが、自ら基準を定めて自ら評価することに慣れていないのがその背景にあります。
現状の購入している全部材について、「サプライヤーとの契約書」「材料証明書」「分析試験結果」の一式を集めるのは、その費用を購入者が負担するのか供給者が負担するのかは別しても、多数回の取引が行われるサプライチェーンを考えると、サプライチェーン全体のコストアップとなり、コスト競争力を弱めている可能性があります。
サプライヤーの負担を軽くするには、「特定化学物質の含有確率を低くする」ことと「供給者の格付けを高くする」ことです。
「特定化学物質の含有確率を低くすること」の対応は、購入者側の設計変更、使用材料仕様変更や有害物質を使わない工程への変更が基本となります。「供給者の格付けを高める」には、組織として特定有害化学物質に関する管理能力を高めることが必要となります。
例えば、はんだ付け工程を考えます。「鉛フリーはんだ」の使用となりますが、同一作業場内で他の顧客要求による有鉛はんだ(共晶はんだ)を使っていれば、含有リスクは高まります。鉛フリーはんだ作業場と共晶はんだ作業場を物理的に話して隔離すれば、コンタミや作業ミスによる含有確率を低く抑えることができます。サプライヤーの管理力は、「鉛フリーはんだ」の購入管理やディップ槽のドロス管理が重要要素になります。
これら工程管理、サプライヤーの管理力は、マネジメントシステムにより確実になります。
最近の関係者の関心としては、購入者側と供給者の双方共に、リスク管理や欧米的な自主的決定を理解しつつも、製品含有化学物質管理の統一的な評価の基準を待ち望んでいます。
製品含有化学物質管理のガイドラインとして、ISO9001をベースにしたRoHS指令やREACH規則の要求事項を念頭に置いたJIS Z 7201があります。JIS Z 7201の3.6項(製品含有化学物質に関するマネジメントシステムの評価)のなかで「必要に応じて、製品含有化学物質管理を実施する組織が、適合性評価及び宣言を行うことができるように、この規格が規定する原則及び指針に関連付けた製品含有化学物質に関するマネジメントシステムの要求事項を文書としてとりまとめることができる」としています。
最後に筆者から以下を提案します。
多様な業界、多数の企業と取引をしている川中の中小企業の立場からは、対応は一本化が望まれ、国内サプライチェーン共通で、さらに欧中共通のマネジメントシステムが望まれます。
このような状況を踏まえて、「ここが知りたいRoHS指令」「ここが知りたいREACH規則」の執筆陣とISO9001に造詣が深いIQAIが連携し、JIS Z 7201の3.6項の解釈のひな形として、仮称「ISO-RoHSガイダンス文書案」を作成しました。
川下企業の要求に真面目に応えるために苦慮している川中の中小企業を日常的に支援している組織として、この窮状を打破したいとの思いでとりまとめたものです。
このガイダンス文書は広く公開し、それぞれの利用者がそれぞれの立場、それぞれの場面で自由に使っていただき、JIS Z 7201ベースとしたEN50581の要求にも合致したマネジメントシステムのデファクトスタンダード化を念願しています。
ガイダンス文書は検討案ですが、以下でダウンロードできるように作業中です。
〇NPO法人国際品質保証協会(IQAI)
〇一般社団法人東京環境経営研究所(TKK)
1)/well/rohs/column/121026.html
3)/well/rohs/column/121109.html
(松浦 徹也)